
コペンハーゲン会議(COP1 5)の意味と今後の地球温暖化対策
─グリーン経済への早急な移行を─
1. COP1 5とは、どのような会議だったのか
国連気候変動枠組条約第15回締約国会議(COP15)は、2009年12月7日から2週間にわたりデンマークのコペンハーゲンで開催され、「コペンハーゲン合意に留意」との決議を採択して終了した。COPはこれまで15年にわたり、毎年、開催されてきたが、今回ほど、その評価が分かれたことはなかったように思われる。
アメリカのオバマ大統領は、会議後「前例のない、ブレークスルー」であったと述べたのに対し、 EU議長国のスウェーデンのラインフェルト首相は大失敗であったと記者会見で発言している。ドイツのメルケル首相は、「国際的気候変動体制に向けた、ささやかではあるが第一歩」と評価している。〔CEPS Commentary, “The Copenhagen Accord: A first stab at deciphering the implications for the EU", Christian Egenhofer & Anton Georgiev, 2 5 December 2 0 0 9, http://www.ceps.eu/book/copenhagenaccord-first-stab-deciphering-implications-eu 〕一方、コペンハーゲン合意に反対したスーダンの代表(開発途上国のグループであるG77 の代表でもある)は、「気候変動交渉として史上最悪の進展」と酷評し、「このままでは、温暖化がもたらす洪水や干ばつの影響により、アフリカで死者が広がる」としている。〔毎日新聞、2009年12月20日、東京朝刊〕オバマ大統領としては、「最終日までの膠着(こうちゃく)状態と決裂の危機から、なんとかコペンハーゲン合意をまとめた」との自負があったと思われる。一方のEUの立場からは、「事前の期待が、ほとんど盛り込まれなかった」との思いがあろう。
このような評価のギャップは、各国や関係者のポジションと事前の期待によって異なってくる。COP15 のそもそもの目的は、京都議定書の第1約束期間後(2013年以降)の気候変動に関する法的拘束力を持った新たな国際合意の形成であった。しかし、バリでのCOP13(08年12月)以降、2年間近くに及ぶ事前交渉の進展がはかばかしくなく、09年の夏ころには、COP15 で法的拘束力のある合意がほとんど不可能であることは、関係者の間では共通の認識となっていた。
こうした状況を背景として、議長国デンマークは各国の首脳に直接に参加をよびかけ、政治的なリーダーシップの発揮によって膠着状況を打破し、「気候変動に関する新国際秩序」の構築を目指した。これに応えて、119 か国にも及ぶ首脳が参加することとなり、COP15 は、ニューヨーク以外では史上最多の首脳が参加した国際会議となった。気候変動問題が、首脳が直接に協議する平和と安全保障に直結するハイ・ポリティックスに、史上初めて押し上げられたのである。はたして、このような賭けは成功したのだろうか。
2. COP15 の結果はどのような内容か
それでは、COP15 はどのような結果となったのだろうか。
COP15 では、(1)京都議定書3条9項に基づく先進国(附属書Ⅰ国)の2013年以降の約束に関する交渉(先進国の2020年目標など)と、(2)条約の下に設置された長期的行動に関する交渉(アメリカと開発途上国を含む)、の2つの作業部会での交渉が進められた。しかし、事務レベルおよび閣僚レベルでの交渉は難航し、それぞれの部会では議長案は提示されたものの合意に至らなかった。そして2週間の会期の最後に、議長国デンマークやアメリカのオバマ大統領が中心となり、まさに最終日の12月18日に、26 の国と地域の代表により、コペンハーゲン合意案が作成された。COP15 は会期を1日延長し、翌19 日に「コペンハーゲン合意」に「留意する」との決定を採択して終了した。〔「留意」となったのは、一部の国(キューバ、スーダン、ツバル、ベネズエラ、ボリビア)が、合意案の作成過程の透明性と公正性の欠如を理由に、採択に反対したためである
その主な内容は、以下のとおりである。〔「気候変動枠組条約第15回締約国会議(COP15)・京都議定書第5回締約国会議(CMP5)等の概要」、2009 年12月20日、日本政府代表団http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=14761&hou_id=11933 〕
(1) 世界全体としての長期目標として、産業化以前からの気温上昇を2℃以内に抑える。
(2) 附属書Ⅰ国(先進国)は2 0 2 0 年の削減目標を、非附属書Ⅰ国(開発途上国)は削減行動を、それぞれ付表1と2に記載する。各国は2 0 1 0 年1月3 1日までに記載事項を提出する。
(3) 締約国の行動はMRV(測定/報告/検証)可能なものとされなければならない。非附属書Ⅰ国(開発途上国)が自発的に行う削減行動も国内検証を経たうえで、国際的な協議の対象となる。支援を受けて行う削減行動は国際的なMRVの対象となる。
(4) 先進国は、2 0 1 0 .1 2 年の間に3 0 0 億ドルの新規かつ追加的な資金による支援を共同で行い、また2 0 年までには共同して年間1 0 0 0 億ドルの資金動員目標を約束する。
(5) 2 0 1 5 年までに(長期目標を含め)合意の実施状況を評価する。
3. COP15をどう評価すべきか
COP15 に対するそもそもの期待、すなわち、京都議定書に続く法的拘束力を持った国際枠組の合意を得る、との観点から判断すると、その結果は明らかに失敗だ。なぜならば、「コペンハーゲン合意に留意する」との決定は、各国に現実的かつ検証可能な義務、とりわけ法的拘束力のある排出数値目標や資金援助を課すものではないからである。
しかし、次のような分野では重要な進展があったといえる。
第1に、「世界全体としての長期目標として、産業化以前からの気温上昇を2℃以内に抑える」との認識が、共有されたことである。この科学的認識は、今後の世界の温暖化対策の強化のよりどころとなるものである。ただし、この目標を達成するための堅実な道筋の合意には至っていない。世界全体の削減量については、「大幅な削減が求められる」としただけで、IPCCが示す「2050年までに少なくとも50%削減」との認識は共有できなかったし、先進国による20年までの削減の中期目標も、既述のように本年1月中に報告が求められるにとどまった(その内容については後述する)。
第2に、資金問題と適応対策、森林減少対策の分野で、重要な進展があったことである。
コペンハーゲン合意に基づく先進国による資金供与の約束は、資金問題の停滞を突破するとともに、炭素市場にも弾みをつけることが期待される。さらに、2010年から12年にかけて300億ドルの新規かつ追加的、予測可能で十分な資金が、「削減」と「適応」とにバランスよく配分されることになった。とくに適応基金がもっとも脆弱(ぜいじゃく)な国を優先することとされ、適応に関する行動と協力(とりわけ最貧国、開発途上小島嶼(とうしょ)国、アフリカを対象)を行うことに緊急の注目が寄せられた。これが、脆弱途上国の最大の懸念に応える道を開くようになることが期待される。
森林問題については、森林減少・劣化による温室効果ガス排出の削減(REDD:Reducing Emissions from Deforestation and Degradation)と、森林による吸収を強化することの重要な役割を認識し、そのような活動を促進するために、先進国からの必要な資源を動員するためのメカニズム(REDDプラスを含む)を早急に設立することが認識された(「コペンハーゲン合意」第6項)。
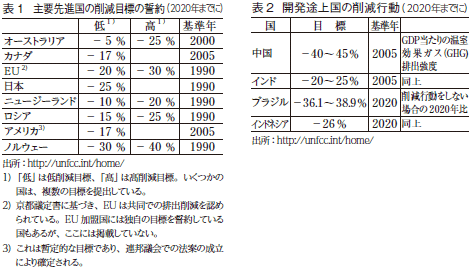
4. COP15以降の展開が重要
COP15 の首脳レベルの会議では、各国首脳が直接に協議することにより、膠着状態を打破したいとの期待があった。しかし、膠着状態の原因は、各国のトップが各国代表に指示した交渉ポジションそのものにあった。ポジション自体が簡単に変更できないものであれば、首脳会談でも打破できない。COP15 の交渉の鍵を握ったのは、アメリカと中国のポジションであった。ところが両国とも国内的事情から、首脳が参加しても事前のポジションを変えることはできなかった。すなわち、アメリカでは上院での温暖化対策法案が成立していないことから、オバマ大統領も「2020年までに05年比17%削減(1990年比4%削減)」との目標に上積みはできない。一方、中国では高い経済成長率の維持が、政治的に至上命題であったのである。また、京都議定書交渉時は、先進国の削減目標が中心議題となっていたので、アメリカ・EU・日本の3極での交渉が中心となったが、コペンハーゲン合意の取りまとめは、アメリカと中国やインド・ブラジルなどとの交渉が先行し、EUや日本はその追認を迫られる形になり、EUと日本の影が薄かったことは否めない。
COP15 の結果が今後の重要な一歩となるかどうかは、今後の展開次第である。コペンハーゲン合意は自動的に次期枠組交渉の基礎になるものではなく、コペンハーゲン合意での前進点を次期交渉につなげ、明確でない事項・合意されていない事項をどのように合意し、次期枠組を形成するかが課題である。
先進国の数値目標と開発途上国の削減行動は、各国が自発的に誓約し、その実施を約束する形となった。2010年1月末までに、条約事務局に提出された先進国の削減目標と開発途上国の削減行動の主要なものは別表の通りである(表1と表2)。
残念ながら、これらの誓約の数値では、コペンハーゲン合意が求める「世界全体としての長期目標として、産業化以前からの気温上昇を2℃以内に抑える」ことは、とても実現できない。民間の研究グループであるクライメト・アクション・トラッカーの推計によれば、「誓約を総計しても、2100年に温度上昇は3℃を越えてしまう」とされている。〔Climate Action Tracker, Press release of 2 February 2 0 1 0 http://www.climateactiontracker.org/ pr_2010_02_02.pdf 〕

写真1 ヘデゴーCOP15議長とボア気候変動枠組条約事務局長に
「公正で積極的かつ法的拘束力のある取り決め」を求める、世界の若者たち(出典:ENB)
5. 今後の展望─グリーン経済への早急な移行が課題
COP15 では、世界が直面する2つの重要な課題、すなわち「気候変動への挑戦」と「成長と開発と貧困に対する挑戦」に、同時に取り組むことができる、包括的で実効性のある合意が期待されていた。「気候変動のリスクを、国際社会が受入れ可能なレベルにまで低減するために必要な規模で、温室効果ガスの排出を削減すること」、その実現の道筋として、「2050年までに、気候の安定化のために許容される世界全体の排出量を、各国に衡平に配分すること」が、COP15 に求められていたのである。
各国は異なる期待とポジションをもって、この会議に臨んでいた。
第1は、気候変動対策と経済発展との関係への認識である。中国に代表される多くの開発途上国は、温室効果ガス(GHG)の削減は、主として石炭使用への制約から、少なくとも短期的には経済発展への制約になると受け止めている。
先進国は「グリーンな成長モデル」論で、これに答えようとした。これはドイツを中心としてEUで影響力を強めてきた「エコロジー的近代化」論に基づく「緑の産業革命」論、「緑の資本主義」論にのっとっており、再生可能エネルギーや環境技術に戦略的・重点的に投資することにより、経済発展を促進して雇用を確保するとともに、環境への負荷の少ない新たな発展パターンを目指すものである。この流れは、08 年の世界的経済金融危機への対処策として「グリーン・ニューディール」につながり、アメリカでもオバマ大統領の登場とともに、環境・エネルギー政策がグリーン・ニューディールとして体系化され、実施に移されようとしている。EUや日本などの先進国では、GHG抑制対策を、グリーンな成長・雇用と将来の国際競争力の問題として構成してきたのである。
中国指導部もこのような新たな発展パターンの必要性は認識し、積極的な環境投資や再生可能エネルギー普及目標を掲げ、GHG排出強度の改善(GDP当たりのGHG排出を2020年に05年比40 .45%改善する)を約束してはいるものの、体制安定のためには高い経済成長が不可欠との立場は譲れなかったのである。しかし、温暖化による影響は中国にも多大な被害を与え、すでに砂漠化の拡大や黄河の断流など、気候変動が原因(または原因のひとつ)とされる被害が顕在化している。
先進国がグリーン成長論で開発途上国を説得するためには、「低炭素成長の実現可能性と実例」、そして「それが、開発途上国でも可能で、利益をもたらすものである」ことを示さなければならない。
第2は、GHG削減に誰が責任を負うのか、そして将来の許容される排出量の配分問題である。各国の責任に関しては、気候変動枠組条約では、これまで「共通だが差異のある責任」が受け入れられている。この原則は、気候変動への対応の責任とコストは、富と能力と歴史的責任を考慮して分担されるべきであるとの考え方である。京都議定書において、先進国にのみGHG抑制目標が課されたのは、この原則が背景にあった。
開発途上国は、この原則に基づき産業革命以来の先進国の歴史的な責任を、国際交渉の場で強調してきた。さらに開発途上国の一部は、炭素負債の議論として構成し、「開発途上国が行動を起こす前に、先進国がまずはその負債を、GHG 削減または財政支援の形で返済すべき」と主張した。しかし、産業革命前と比較し温度上昇を2℃以内に抑えるためには、2050年までに、少なくとも50%の削減が求められており、これは明らかに新興国の排出抑制なくしては達成できないので、先進国の大幅削減に加え、開発途上国においても温暖化緩和の行動が求められているのである。先進国はそうした行動に対する支援の強化が求められ、これが資金援助および技術移転の課題となっている。
第3は、気候変動の影響に対する適応対策である。多くの新興国および開発途上国にとって、気候変動問題は、適応問題がより重要で切迫している。異常気象による影響が、これらの国でとくに顕在化しているのである。とりわけ、最貧開発途上国は対処能力が乏しいので、もっとも脆弱である。COP15 では、資金問題と適応対策には一応の進展が見られたが、コペンハーゲン・グリーン気候基金をできるだけ早く発足させるとともに、これらの約束の実効的かつ効率的な実施が必要である。

写真2 二酸化炭素1トンの風船(筆者撮影)
6. 日本はどうすべきか─ 低炭素社会への動きは止められない
日本は条件付きながらも、2020年に1990年比でGHGを25%削減する目標を誓約し、気候変動枠組条約事務局へ提出した。
COP15以降の当面の国際交渉の動向はさておき、2050年には先進国は80%の削減が求められていることも視野に入れると、2020年はその通過点であり、長期的には低炭素社会への移行は不可避である。イギリスでは2020年および2050年目標を踏まえ、その達成の道筋を国内法で書き込んでいる。アメリカでも下院で可決されたワクスマン・マーキー法案や上院で審議中のケリー・ボクサー法案でも、キャップ・アンド・トレード型の国内排出量取引の仕組みや財源につき、詳細な規定が明記されている。
産業界においても、低炭素社会に向けた動きと競争は加速化している。これからの社会は、環境対策が経済発展につながり付加価値と雇用を生み、国際競争力を高める時代が到来し、国はそれを後押しする政策を積極的に導入していくことが期待される。
環境先進国を自負してきた日本は、かつてない目標の達成に向けて抜本的・革新的な改革を進めながら、グリーン技術革新やマーケットの開拓を続けることによってのみ、今後、確実に拡大が見込まれる世界のグリーン・マーケットにおいて、先行者利得と比較優位を確保することができる。そのためにも、成長戦略と環境戦略を統合した日本版グリーン・ニューディールの具体化が必要である。経済的なインセンティヴを設け、新たなマーケットを創出し、技術革新とその普及を進め、それによって雇用も拡大する低炭素型の経済発展のモデルを率先して実現することが、日本の向かうべき道であり、世界への貢献でもある。
鳩山政権は発足早々の2009年9月、国連演説で2020年に1990年比25%削減を表明し、また鳩山イニシアティヴ(開発途上国への援助の約束)によって、コペンハーゲン合意に寄与したことは評価されるべきである。しかし、国際的な信頼と説得力を高めるためにも、この目標の達成を確実にする国内制度の早急な整備が必要である。政府は3月12日、温暖化対策基本法案を閣議決定した。この基本法に基づき、温暖化対策税、総量抑制型国内排出量取引制度、すべての再生可能エネルギーを対象とした固定価格買取制などの早急な具体化が必要である。同時に、COP15以降も衡平で包括的で有効な国際合意に向け、より高度に戦略的な外交努力も必要だ。