
食料安全保障の確立に向けて
1.さらに下がる? 日本の食料自給率
「食料自給は国家安全保障の問題であり、それが常に保証されているアメリカは有り難い」(It's a national security interest to be self-sufficient in food. It's a luxury that you've always taken for granted here in this country.)、「食料自給できない国を想像できるか、それは国際的圧力と危険にさらされている国だ」(Can you imagine a country that was unable to grow enough food to feed the people? It would be a nation that would be subject to international pressure. It would be a nation at risk.)。これは、ブッシュ大統領が国内の農業関係者向けの演説で、しばしば用いるフレーズである。
このように、アメリカは、自らは食料自給率と国家安全保障の関係を非常に重視し、自国の食料生産を手厚く支援している。一方で、余剰処理と食料による世界戦略を進めるため、世界の他の国々には、WTO(世界貿易機関)などを通じて農産物貿易自由化を求め、「非効率な」食料生産をやめて自国から食料を買うよう推進してきた。それにもかかわらず、現在は、長く続いた穀物価格低迷による農家への財政負担増を軽減するために、バイオ燃料需要喚起で穀物価格を上昇させ、食料生産を縮小して海外依存を強めてきた世界の貧しい発展途上国の生活を脅かしたのである。アメリカの自国利益優先の身勝手な行動に、世界が振り回されているという指摘が出るのもやむを得ない。
わが国では、すでに政府間交渉が進んでいるオーストラリアとの自由貿易協定や、次に水面下で準備されているアメリカとの自由貿易協定を、農業分野を完全に組み込んだ「質の高い」(例外品目のない)形で進めたいという経済界の強い意思は、世界の食料事情が一変した今も何ら変わっていない。アメリカ側も、コメを含めた農業分野の例外なき関税撤廃が、日本との自由貿易協定の条件であると主張している。
わが国の平均的な農産物関税は世界的にみても低く、国内補助金も欧米よりもはるかに少ない。だからこそ、世界的にも突出した食料自給率の低さになっているわけだが、わずかに残された重要品目さえも関税撤廃していくと、食料自給率はどうなるのだろうか。
オーストラリアとの自由貿易協定で、かりに例外なしの関税撤廃が行われた場合には、すでに40%しかないわが国のカロリーベースの食料自給率が、30%まで下がるとの試算もある。日豪の自由貿易協定が成立すれば、競合する輸出国も同様の条件を求めてくるであろう。そもそも、次は、日米、日EUとの自由貿易協定が控えているとすれば、事態は世界に対する全面的な自由化と変わらない状況に近づくことを意味する。「農産物貿易自由化の工程表を示すべし」とする経済財政諮問会議のワーキング・グループ会合では、世界に対する全面的な国境措置の撤廃により自給率は12%になるとの試算が農林水産省から提出され、事の重大性が改めてクローズアップされた。うっかりしていると、わが国の食料自給率は、もはや独立国家としての国家安全保障(ナショナル・セキュリティ)を維持できない水準にもなりかねない。国民は、これを許容できるであろうか。
2.「食料は、お金を出せばいつでも買える」わけではない
今回の「食料危機」では、自国民への食料確保への不安から、各国が輸出規制に向かい、それが国際価格高騰を増幅させたことを重く受け止める必要がある。結局、自国民に十分な食料を確保できるか心配になると、国外に出さないように輸出を規制して、自国民の分を確保しようとする。これは、国家の責任として、ある意味で当然である。したがって、日本の主張のように輸出規制があまり簡単に行われないように提案するのも必要ではあるが、むしろ、輸出規制が自国民の食料を守る意味で実施されるのを規制するのは困難であることを認めて、そうであるなら日本のような輸入国もそれに対処して、ある程度の国内生産を常に確保しておく権利が同様にあることを、国際的に確認することが重要だ。
WTOルールにしたがい、また、世界銀行などのアドバイスの下に、穀物関税を引き下げ、基礎食料の輸入依存を強め、商品作物生産に特化した発展途上国は、輸入価格の高騰で、政策の失敗を嘆いている。今のWTOルールは、まさに狭い意味での経済効率だけに基づいて、国際分業、つまり、効率のいいところで農産物を作り、日本のような零細で非効率な農業はなくなってもいいということを前提にしたものである。したがって、今日のように価格が高すぎる、あるいはお金を出してもモノがないような状況で、ナショナル・セキュリティが維持できなくなることに、対応できないルールだということが、明白になったわけである。
この点で、洞爺湖サミットの宣言は、発展途上国の食料増産を支援するとしながら、もう一方で、WTOによる自由貿易を推進するとしており、整合性がとれていない。過度な自由貿易の推進こそが、途上国の食料生産を衰退させ、輸入に頼る構造をまねいたのである。食料増産への支援が実を結ぶためには、単純に関税をゼロに向けて引き下げていくだけの自由貿易推進ではなく、それに一定の歯止めをかけて、各国の食料生産が確保できるようにする軌道修正が必要だということが確認され、それを反映したWTO交渉の合意が図られるべきであった。
3.「WTO決裂」は立ち止まって、食料の国際貿易ルールを見直す良い機会
にもかかわらず、WTOは2008年7月に閣僚会議を開き、一気に合意にこぎつけようとする機運が高まった。しかも、農産物輸出を行っている先進国は、輸入急増による影響緩和措置さえも最小限にするよう、輸入国に対して、市場アクセスの改善を強く要求した。さらに、彼らは、アメリカに代表されるように、自国の国内生産を十分に支援し、余剰を実質的な輸出補助金により海外で処分する「攻撃的保護」は温存したままなのである。
アメリカの穀物(コメ、小麦、トウモロコシ、大豆など)、綿花への市場価格と目標価格との差額を補する補助金は、WTO上は国内政策に分類されているが、実質的な輸出補助金部分を含んでおり、ブラジルの提訴によりWTOパネル(紛争処理委員会)で敗訴した。それにもかかわらず、それを履行しないばかりか、新しい農業法で、補基準の目標価格を引き上げるなど、強化している。
このため、インドや中国が反発したのは当然である。輸出国の「攻撃的保護」装置を放置して、輸入国が関税削減などを大幅に行うことは極めてバランスを欠くので、その点からも、安易な妥協はすべきではなかった。決裂はやむを得ない。今回の決裂は、単純な関税削減の継続に一定の歯止めをかけ、狭義の経済効率だけでなく、貿易自由化が国家の安全保障を弱め、地球環境へ負荷を高めるといった負の影響(外部不経済)を総合的に考慮して、食料の国際的な貿易ルールの見直しのために立ち止まる、良い機会を与えてくれたと考えるべきであろう。
4.関税および補助金の削減と日本の食料自給率の低下
なぜ、わが国の食料自給率が40%にまで落ち込んでいるのかを考えると、日本の食料市場の閉鎖性や農業過保護論の誤りも歴然となる。関税が高ければ、これほどに輸入は増えないし、関税が低くても農家所得を形成する国内の補助金が多ければ国内生産は増えるはずである。そうなっていないということは、どちらも十分に高いとはいえないことが明白である。
つまり、自給率が下がった大きな要因は、端的にいえば、欧米諸国ほどには国産振興策が採られていないことにある。わが国は、国境措置(関税)と国内支持の両面で、農業への支援を削減してきた。であるから、わが国の農産物市場が閉鎖的だというのはまちがいである。日本ほど、グローバル化した食料市場はないといってもよい。我々の体のエネルギーの60%もが海外の食料に依存していることが、何よりの証拠である。
関税削減が自給率の低下につながることは、大豆、トウモロコシ、ナチュラル・チーズ、牛肉、オレンジ・リンゴ果汁などでの経験からも容易に納得できる。牛肉も和牛は大丈夫といわれたが、自給率は40%台に低下したし、果汁の自由化は、わが国のミカンやリンゴの生食需要を奪い、果物の自給率は30%台に低下した。関税を引き下げても、直接支払いなどの拡充で国産の縮小を食い止めることは可能だが、わが国は国内保護の削減にも努力してきたから、関税と国内保護の両面の削減により、食料自給率の低下がもたらされたことは否定できない。
〈わが国の農産物関税が高いというのは誤り〉
わが国の農産物の平均関税率は12%であり、農産物輸出国であるEU(欧州連合)の20 %、タイの35%、アルゼンチンの33%よりもはるかに低い。さらに、品目数で農産物全体の1割程度を占める最重要品目を除けば、他の農産物の関税は相当に低く、野菜の多くはわずか3%で、世界との産地間競争の中にある。わずかに残された高関税のコメや乳製品などの農産物は、日本国民にとっての一番の基幹食料であり、土地条件に大きく依存する作目であるため、土地に乏しいわが国が、外国と同じ土俵で競争することが困難なため、関税を必要としているのである。日本が守ろうとしているのは、わずかに残された最重要品目だけで、いわば、つつましい最低限の望みを訴えているだけなのである。
「高関税で世界に閉鎖された日本の食料市場の開放が必要だ」というのは誤りで、実は「すでに、世界的にも最も開放された日本の食料市場において、わずかに残された最重要品目についても、全面的に関税撤廃すべきだ」という、議論なのである。このことの結末を、十分に考える必要がある。
〈わが国の国内補助金が多いというのは誤り〉
国内保護政策についても、コメや酪農の政府価格を世界に先んじて廃止したわが国の国内保護額(6400億円)は、今や絶対額で見てもEU(4兆円)やアメリカ(1兆8000億円)よりはるかに小さく、農業生産額に占める割合でみてもアメリカ(7%)と同水準である。しかも、アメリカは酪農の保護額を実際の4割しか申告しておらず、実はもっと多額の保護を温存している。
5.欧米輸出国の自給率の高さは、競争力ではなく手厚い支援の結果
しばしば、アメリカは農業の国際競争力があるから、輸出国になり、100%を超える自給率が達成されていると説明されるが、これは誤りである。
わが国が農産物の平均関税率もかなり低く、価格支持政策とはすでに決別し、輸出補助金はそもそもゼロであるのに対して、欧米諸国の農業保護は、今でも高関税・価格支持・直接支払い・輸出補助金の組み合わせによって仕組まれている。
まずは、高関税・価格支持・輸出補助金の3点セットで仕組まれている酪農品について、実態をみてみよう。欧米でわが国のコメに匹敵する基礎食料の供給部門といわれる酪農については、「欧米で酪農への保護が手厚い第一の理由は、ナショナル・セキュリティ、つまり、牛乳を海外に依存したくないということだ」(コーネル大学K教授)、「生乳の腐敗性と消費者への秩序ある販売の必要性から、アメリカ政府は酪農を、ほとんど電気やガスのような公益事業として扱ってきており、外国によってその秩序が崩されるのを望まない」(フロリダ大学K教授)といった見解にも示されているように、国民、とくに若年層に不可欠な牛乳の供給が不足することは、国家として許さない姿勢がみられる。わが国のように牛乳・乳製品の自給率が70%に満たなかったら、欧米では社会不安が生じかねない。
酪農品の国際競争力は、オーストラリアとニュージーランドが突出して強い。そのため、EU諸国やアメリカといえども、輸出力で勝てないのはもちろん、オセアニアからの輸入を制限する防波堤(保護措置)がなければ、国内自給さえ確保することができないのである。そこで、EUもアメリカも乳製品には高関税を課し、国内消費量の5%程度のミニマム・アクセスに輸入量を押さえ込んでいる(ミニマム・アクセスは本来、低関税の輸入機会の提供であり最低輸入義務ではないから、実際は枠が未消化の場合が多い)。その上で、国内の余剰乳製品は政府が買取価格を設定して買い入れ、過剰在庫が生じれば、輸出補助金を使った輸出か、食料援助によって海外市場に仕向けられる。こうして行われる食料援助は、実質的に、輸出価格ゼロ(全額補助)の究極の輸出補助システムともいえる。
つまり、高関税によって輸入を閉め出し、国内で手厚い価格支持を行えば、必然的に過剰生産が生じて国内価格の下落を引き起こすのだが、過剰分は補助金を付けてダンピング輸出(または食料援助)されるため、問題は解消されるのである。こうして、本来ならオセアニアからの最大の輸入国になるはずのEUやアメリカが、逆に輸出国になり得ているのである。決して競争力があるから輸出しているのではない。一方、わが国は、過剰生産が出ると生産調整を強化する選択肢しかもたない点で、農業政策の体系が全く異なっている。
穀物でも、状況は類似している。酪農だけでなく、アメリカの穀物や綿花も同様で、手厚い国産振興策が国内需要をはるかに上回る生産を生み出し、そのハケ口が実質的な輸出補助金で用意され、結果的に100%を超える自給率が達成される構造を見落としてはならない。
その代表例であるアメリカのコメの価格形成システムを、日本のコメ価格水準を使って説明しよう。たとえば、コメ1俵当たりのローンレート1万2000円、固定支払い2000円、目標価格1万8000円の場合、生産者が政府機関にコメ1俵を質入れして1万2000円借り入れ、国際価格水準4000円で販売すれば、その4000円だけを返済すればよい(マーケティング・ローンと呼ばれる)。これに加えて、固定支払いとして2000円、および目標価格1万8000円と「ローンレート+固定支払い」との差額4000円 (いわゆる「復活不足払い」)も政府から支給される。このローンレート制度を使わない場合でも、1俵4000円で市場で販売すれば、ローンレートとの差額8000円が政府から支給される。つまり、生産費を保証する目標価格と、輸出可能な価格水準との格差(ここでは1万4000円)が、3段階の手段で全額補される仕組みである。
イギリスが一度低下した自給率を高めることに成功した大きな理由も、EU加盟により、EUの共通農業政策に基づく手厚い農業支援を受けられるようになったことであり、やはり保護の結果なのである。
〈農業所得に占める政府からの支払い〉
以上のような欧米諸国の農業支援の手厚さを集約して物語る指標がある。それは、農業所得に占める政府からの直接支払いの割合であり、たとえば、フランスで8割、スイスの山岳部では100%ともいわれ、アメリカの穀物農家でも、年によって変動するが、平均的には5割前後である。日本の場合、稲作におけるサンプル調査結果では、せいぜい2割強(JA共済総合研究所の調査に基づき、渡辺靖仁主任研究員が試算した暫定値)というデータもあり、大きな開きがある。
このように、わが国の自給率の低さは保護水準の低さの証であり、欧米諸国の自給率および輸出力の高さは、手厚い保護の証ともいえるのである。
5.国民の意識と行動の差異も大きい
さらなる食料自給率の低下を回避するには、将来の日本社会、国土のあり方を見据えて、さらなる食料市場開放の是非について十分に議論することが重要である。しかし、関税削減がさらに進むことをある程度前提とせざるを得ないとすれば、それでも日本の消費者が国産農産物を選択してくれるような「生産者と消費者の絆」を形成しうるか、という点が問われる。
〈消費者は高くても国産を買うか〉
スイスについて、次のような話を聞いた。あるスーパーで、国産の卵は一個約60円で、輸入卵は約20円。それでも、ほとんどの人が割高な国産卵を買っていく。「なぜ、高い方を買うの」とお客にたずねると、「これを買うことで、農家の生活が支えられ、それで私たちの生活が支えられる」。こう答えたのは小学生だった。このような関係を、わが国でも築けるであろうか。
また、数年前のことだが、イタリアのナポリの牛乳は1リットルが約200円で日本より高かった。EUの他の国々から、もっと安い牛乳が入ってきてもおかしくない。これは、スローフード運動に象徴されるように、少々高くても、地元の味を誇りにし、消費者と生産者が一体となって、自分たちの地元の食文化を誇りに思い、守る機運が生まれているからである。
〈価格に反映されない価値を、直接支払いで〉
さらに、北イタリアの水田地帯では、稲作農家に対して、水田の持つ水質浄化機能、オタマジャクシやトンボなどが棲息できるといった生物多様性の維持、わが国でも指摘はされるが十分評価されていない洪水防止機能を評価して、それらは米価には反映されないが、住民が利益を得ている部分であるから、それに対する対価は別途支払うべきとの考え方に基づいて、他の畑作経営に上乗せした直接支払いを行っているという。先述のフランスの農業所得に占める政府からの直接支払いの割合が8割という数字に象徴されるようなEU各国における直接支払いの充実は、こうした環境面での評価や、さらには美しい景観の維持も含めて、食料生産の持つ多様な価値への国民の理解が得られているからこそ、可能になっていると思われる。
このような多面的機能は、農家の経営規模の大小を問わず発揮される、あるいは、棚田の景観や洪水防止機能でわかるように、むしろ条件不利な地域の小規模農家のほうが評価が大きい場合もあるから、小規模農家や中山間地域の支援の大きな根拠になる。しかし、わが国では、こうした直接支払いの充実に向けて、バラマキとはいわれない、国民にも納得できる理由が十分に説明されてきただろうか。「農家が困るから」というだけでは、国民に説明したことにならない。農業農村には多面的機能があるからといっても、十分に具体的な指標になっていなければ、国民には、むしろ保護の言い訳のように受け取られてしまう。可能なかぎりの具体的な指標を基に、消費者と生産者が「安さ」と引き替えに失うものの大きさを一緒に考える場を、もっとつくるべきである。漠然とした「多面的機能」ではなく、基礎食料の海外依存リスク、カーボン・フット・プリント(生産・流通の全行程でのCO2排出量)、バーチャル・ウォーター(国際的な水使用による環境負荷)、生物多様性、等々の外部経済指標を狭義の経済指標と併せて、総合的に判断することが国内的にも重要であるし、それをWTOルール見直しの具体的提案につなげなくてはならない。
簡単な試算例で示すと、表1のように、WTOによるコメ貿易自由化によって、生産者の損失と政府収入の減少の合計は約1兆1000億円にのぼるが、消費者の利益が約2兆1000億円にのぼるため、日本トータルでは、1兆円の「純利益」があるというのが、狭義の(外部効果を考慮しない)経済指標の変化で、これがWTOの自由化推進の大きな根拠である。
しかしながら、同時に、表1は、わずか数%というようなコメ自給率の大幅な低下によるナショナル・セキュリティの不安、水田の減少による窒素過剰率の1.9倍から2.7倍への大幅増加による環境負荷・健康リスク(乳児の酸欠症、消化器系がん、糖尿病、アトピーなど)の増大、バーチャル・ウォーターの22倍の増加(水の豊富な日本で大量の水を節約し、すでに水不足の深刻な輸出国の環境負荷を高めるという国際的な水収支の非効率を生む)やフード・マイレージの10倍の増加による環境負荷の大幅増大(コメの輸送によるCO2排出が10倍になる)、カブトエビ43.9億匹、オタマジャクシ384.1億匹、秋アカネ3.6億匹の死滅という生物多様性の損失、といった価値は勘案されていない。
食料自給率の低下、およびそれに付随するこれらの外部効果指標は、表1のような技術指標としての数値化は可能だが、それを簡単に金額換算して、狭義の経済性指標の純利益の1兆円と、単純に比較できるものではない。しかし、だからといって、狭義の1兆円の利益よりも軽視されていいというものではない。社会全体で十分に議論し、さまざまな人々の価値判断も考慮し、適切なウエイトを用いて、総合的な判断を行うべきものであろう。
現行のWTOでは、狭義の経済性指標のみに基づき、継続的に一律的な関税削減を行う道筋になっており、このままでは、仮に、その速度を緩めることができても、やがて関税がゼロになる流れの途上にあることを重く受け止めなくてはならない。総合的指標をWTOルールに組み込まない限り、この流れを止めることはできない。
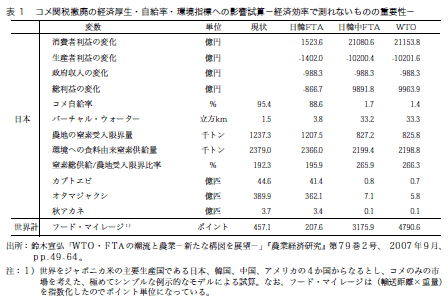
6.「生産者と消費者の絆」の強化と農家に届く施策の集中化
さらなる食料自給率の低下が懸念されるなか、これ以上の食料貿易自由化の徹底が本当に日本のあるべき姿なのかについて十分な議論が不可欠であるとともに、どんな状況においても消費者が国産を選択するような生産者と消費者の絆ができるかどうかが重要である。生産者は、この人が作るものなら大切に食べたいと消費者を自然に引き付けるような、根本的なところで、生命の維持に不可欠な食料を、その生産過程も含めて、最良の形で消費者に届けるというミッション(社会的使命)に誠意を持って取り組み、消費者がこれをしっかり受け止めて支えてくれるシステムのさらなる強化が必要である。そうなれば、コスト高になったときは、高い価格でも支え、価格に反映できなくても、財政から多様な価値への対価として支援することへのコンセンサスも生まれよう。価格には反映されていない食料生産の価値をEUのように評価し、直接支払いの拡充を進める必要がある。バラマキではない具体的根拠を示し、それを消費者が納得し、生産者もその役割を誇りにして取り組む関係を成立させなければならない。
欧米と比較すると、わが国の農業補助金は総額としても少ないが、さらに、農家の所得に直接的に結びついている部分の少なさも目立つ。日本の農業政策には、さまざまな政策メニューがあるが、それらを集約して、より直接的に農家の所得形成につながるような政策に集中的に予算配分することも検討されてよかろう。そのためには、国の補助金は団体や組織に支払えても、個別農家に支払いにくいという、わが国の予算執行上の問題も検討される必要があろう。また、思い切った予算の再編や拡充ができない現行の財務省による査定システムを見直し、国家戦略、世界貢献として、省庁の枠を超えた、一段高いレベルでの国家全体での予算配分を行うべきときが来ていると思われる。