
G8の食料安全保障声明から見えてきたもの
世界各地で相次いだ食料暴動や穀物輸出規制などの「食料危機」にどう立ち向かうのか。2008年7月に開かれた北海道洞爺湖サミットは主要な議論の一つに食料安全保障を位置づけた。主要先進国首脳(G8)サミットは、食料に限定した「世界の食料安全保障に関するG8首脳声明」をまとめ、力を合わせて危機の突破にあたることを表明した。実際には各国間の足並みの乱れもあって、具体的な対策は盛り込まれなかった印象が強い。なぜ、G8は食料安保を取り上げたのか、そして日本は不安定な食料需給のなかで何をするべきなのだろうか。
サミット取材は、基本的にすべて洞爺湖にあるウインザーホテルから車で30分離れたメディアセンターで行われた。会合に関する情報説明は、ほとんどがテレビ電話でホテルとセンターを結び行われた。最終日に首脳らがセンターに来場し、記者会見を開いたものの、得られる情報は限られ、サミットの雰囲気を知るのはむずかしかった。首脳会談や拡大会合などサミットそのものの行事も、ごく限られた代表を除いて非公開。センターのあちこちにある公式テレビ放送を見上げながら、メモをとる内外の記者の姿ばかりが目についた。こうした公式会合の背景を知るには、ブリーフィング直後に説明にあたった当局者に食い下がって得られる、一言二言が重要な役割を果たすのだが、この「ぶら下がり」ができなかったことも、生の情報を得る上で障害となった。

写真1 北海道洞爺湖サミットで協議するG8のメンバー(提供:日本政府)
情報閉鎖の傾向は日本だけに限ったわけではなく、例えばアメリカ政府も似たり寄ったりのところがあった。メディアセンターに隣接するホテルの一角に、アメリカ政府は大きなプレスセンターを開設したものの、対象は「ホワイトハウス記者証」を持っているジャーナリストだけが対象。「プレスセンターの経費はすべて、ホワイトハウス記者証を持つ人たちで分担しているため、その他の人にはご遠慮願っている」(在日アメリカ大使館報道部)というのが理由。何のことはない。みんなで、内輪の話をあまり外に出さないようにしていたのだ。
決して神秘性を高めることでG8の権威を保とうとしたのではない。首脳同士が率直な意見を交換するというサミット本来の趣旨から、シェルパと呼ばれる一握りの高級官僚たちによる事前のすりあわせ主導型に変質する中で、「生」で会合を取材する意味が薄れてきたことを象徴しているように思える。多数の二国間会談、たっぷりとした会食などイベントを含めて、たった3日間の会合にG8プラスアフリカ諸国や中国、インド、ブラジル、韓国など、その他の主要国首脳、国際機関トップなどが入り混じって、本音の議論ができるとは考えにくい。メディアセンターで話を聞いた多くの海外ジャーナリストも、同じような意見を持っていた。
本音の議論が行われなかったのは、食料安保に関する声明でも同じだ。
G8のワーキング・ミーティング直後のテレビによるブリーフィング会見で、筆者は直接食料安保声明に関わるG8の話し合いの中身を確認しようと質問した。
「G8会談のなかで、食料安保の声明がどのような議論を経てまとまったのか教えてほしい」(筆者)
「特段の発言はありませんでした」(日本政府関係者)
「……」(記者団)
つまり、食料安保の声明は事前のシェルパの議論の段階で内容が煮つまり、首脳らの間で具体的な話し合いが行わなかったというのだ。G8の直前に開いたアフリカ諸国との首脳らと会合では議論になったが、G8という枠組みでは事務局から上がってきた声明文書を、そのままG8決定という冠をつけて発表されたというのが真相だ。
「それでも主要国の首脳の合意というかたちで、食料安保というテーマが取り扱われた意味は小さくない。なかでも日本を含めた世界各国で食料増産の必要性で一致できたことは、これから日本が農業振興を進める上で足がかりになる」と農水省の幹部はサミット後に解説した。首脳らによる白熱した議論はなくても、公の首脳声明で文書が残れば、目的の多くは達成できたという考え方だ。
G8を舞台にした、初めての食料安全保障声明にたどり着いた経緯を振り返ってみよう。
「G8の場で食料安保が主要な議題になる」という情報が、少なくとも国内の公の場で浮上したのは、2008年4月8日だった。自民党総合農政調査会の保利耕輔会長(当時)が「政府首脳に対して、食料自給率の向上と食料安全保障については、サミットの場でも、しっかりと考え方を述べるよう要請したい」と、東京都内で開いたJA全中のWTO農業交渉対策全国代表者集会でぶち上げた。保利氏が挙げたのは地球温暖化、バイオ燃料、中国などの食料需要の増加を背景にして世界の食料需給が不安定になっており、首脳レベルで認識を統一した方が良いというのが趣旨だった。
日本農業新聞は翌9日付でこの情報を大きく報道したが、他のメディアはほぼ黙殺。この時点で本気でG8サミットの議題の一つになると考えていた人はほとんどいない。正直に言えば、筆者も原稿を読んで「この話、本当かよ」と思った一人だ。しかし、イギリスのブラウン首相など、海外の有力なG8メンバーらが相次いで世界の食料問題の重要性を強調したほか、国際機関の側からも、G8で食料安保を論じるべきだとの気運が急速に高まった。
潮目の変化を明確に示したのが、世界銀行のゼーリック総裁が4月13日にワシントンで開いた世界銀行と国際通貨基金(IMF)の合同開発委員会で行った演説だった。世界中で高まる食料価格の影響により、貧困国で餓えや死に至る激しい暴力が生じていることに対する緊急対策を行うべきだとして、国際社会が農業および食料分野で足並みをそろえる必要性を強く訴えた。アメリカの住宅バブル崩壊を契機に世界の経済が乱気流に突入し、どのように経済の立ち直りを図るかが最大のテーマとみられていた。ところが「発展途上国にとっては食料危機の方が深刻」という声が途上国側から噴出し、「ゼーリック氏も農業重視の姿勢を打ち出さざるをえなかった」というのが、欧米メディアの指摘だった。
発展途上国など国際世論の背中を押したのが国際穀物相場の急騰だ。たとえば、コメの国際相場(バンコクの長粒種輸出価格)は1月初めの段階から3倍に値上がりし、4月には1000ドル/トンを超えた。フィリピンの国家元首であるアロヨ大統領は、高まる国内の不安に応えるため、隣国のベトナムのズン首相にコメの融通を懇願するなど、国際市場のコメ逼迫観は高まった。トウモロコシや小麦なども高騰した。ハイチやアフリカの各地で食料を求める暴動が相次いだ。
しかし、筆者はG8が食料安保を自らの問題として議論することを決めたのは、価格高騰の波が自国民のテーブルまで押し寄せてきたからだと考える。
冷酷なようだが、世界で食料不足そのものは珍しいものでも何でもない。世界中で8億人以上の人たちが腹を空かし、局地的に内戦や災害が起こると、数万から数十万人が飢餓で命を落とす。2015年までに貧困や飢餓を半減しようという国際社会が合意したミレニアム開発目標(MDGs)にしても、現実の飢餓の存在を前提としている。
G8に参加する首脳にとって、それらは心が痛む問題ではあっても、自らの政治生命を脅かすものではない。しかし、いったん国内でインフレが始まり、国民の生活が圧迫されれば、それは政治生命を左右しかねない問題だ。日本を含めた先進国で、チーズやバターの価格が上昇し、穀類、食肉や卵の値段が上昇している以上、「G8として放置できない」というメッセージを発信する必要があったのだろう。
6月にローマで開いた国連食糧農業機関(FAO)の「世界の食料安全保障に関するハイレベル会合」(食料サミット)は、世界的な食料価格の高騰に対応するため、「緊急かつ協調した行動」を取るよう国際社会に呼び掛ける宣言を採択した。食料安全保障を「恒久的な国家の政策として位置づけることを誓う」と表明した。日本が主張した各国の食料増産の必要性も盛り込まれた。こうした流れの延長線として、G8の声明がまとめられた。
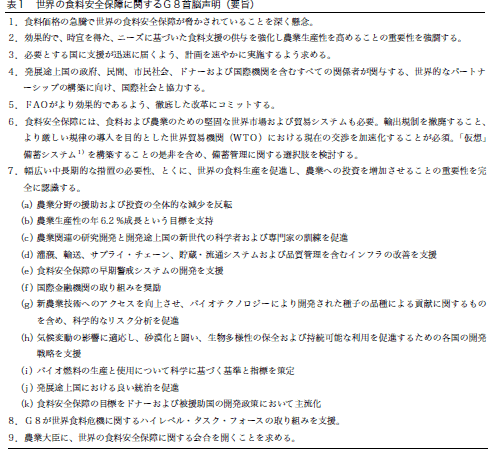
日本政府は、G8で食料問題を取り上げることに前向きだった。大量の輸入農産物に依存し、食料自給率の引き上げ目標を政府として掲げている日本にとって、食料安保という言葉が国際社会で重みを持つことが悪いはずがない。そこで日本政府はG8の歴史で初めての食料安保に関する声明をまとめ、その中にできるだけ日本にとって有利な文言を滑り込ませようと調整を始めた。
その際に日本政府がこだわったのが、日本などの先進国を含めた世界全体の農業生産の底上げと、食料輸出規制の撤廃という概念を文書の中で明確に位置づけようとした点だ。食料価格急騰のなかで、世界の食料増産を奨励することは当たり前のことだが、G8メンバーの間には微妙な立場の違いがある。日本は「先進国を含む各国が自分の食料に責任を持つことが必要で、みんなで増産しよう」という主張。一方でアメリカなどは「アフリカなどの途上国で増産するのを支援することは当然だが、豊かな先進国は食料輸出国から買えばよい。増産はアメリカなどの食料輸出国が担う」という姿勢だ。あまりに食料増産というキーワードだけが歩き出すと、食料輸入国に有利となり、世界貿易機関(WTO)の農業交渉で焦点の一つになっている市場開放の議論に悪影響が出かねないと、アメリカなど輸出国側は心配した。
結果とすると、食料の増産を途上国に限定することなく幅広い文脈で促すこととなり、日本政府の主張が反映された。
もう一つの食料輸出規制の問題では、直前までG8の足並みがそろうかどうか疑問視されていた。
前述のローマのFAO食料サミットでも、宣言案づくりで輸出規制をどのように取り扱うかで各国の意見が鋭く対立した。先進国側は世界銀行などとともに、国際食料市場のかく乱要因になるとして、輸出規制には強く反対していた。とくに日本などの食料輸入先進国は、これまでの通商交渉で自国の農産物市場を開放し続けて譲歩を重ねてきたが、一方で輸出国側が自分の都合で輸出を差し止めるようなことに強い不満を抱いてきた。WTO農業交渉の場などで、輸出国側にも「規律」を強く求めていた。
しかし、途上国の事情は複雑だ。例えばインドは自国の需給が逼迫すると、遠慮なく輸出を差し止める。2007年からコメに最低輸出制度を導入して事実上、香り米ではない普通の白米の輸出を禁じた。さらにG8サミット直前の7月に入ると、トウモロコシの輸出を10月まで禁止した。ベトナムやアルゼンチン、スリランカ、ウクライナなども輸出を制限した。3月に訪問したハノイで取材に応じたベトナム政府関係者は「自国民を犠牲にしてまで、食料を輸出することはできない」と明確に、輸出規制が正当な権利であると主張した。同じように、フィリピンの国際稲研究所(IRRI)で3月に会ったインドの政府系研究機関の幹部も、「飢餓輸出など、とんでもない」と筆者の質問に答えている。多くの国民が穀物から栄養を摂取する中で、たとえ足りなくても目の前の食べ物を海外に出せというのは「正義ではない」(インドの研究者)という論理だ。これはこれで、説得力があるようにも思える。
発展途上国の比率が高いFAO食料サミットでは「制限的な措置の利用を最小限に抑えることの必要性を確認」という、弱い調子の自粛論で落ち着いた。
「先進国で構成されるG8では、もう少し強い調子で議論をまとめたい」
外務省の関係者は、FAOの会合後、G8サミットに向けてこのような解説をしていたが、結果的には別表のように、「食料の輸出規制の撤廃」の必要性が声明に盛り込まれた。
ただ、これも最終局面まで不確定要素があった。G8メンバーのロシアの対応である。ロシアは月に100万トンを上回る規模の小麦を売る大輸出国である。それが昨年、国内のインフレ対策を理由にして輸出税を突然引き上げブレーキをかけた。天然ガスや石油などを含めて資源外交を強めるロシアにとって、自ら手を縛るような食料輸出規制の撤廃は安易に飲めるようなものではないと見られていたが、これもG8サミット直前の6月末になって、引き上げた輸出税を撤廃し、G8の場では他の先進国に足並みをそろえた。
こうして、食料の増産と輸出規制撤廃という2つを柱に加えたG8の食料安保声明はまとめられた。
ただ、G8でまとまった食料安保声明の実効性には疑問が残る。声明の中で「加速化」を唱えたWTO交渉は、1か月も経たないうちに再び暗礁に乗り上げた。
国際的に注目が集まったのは、バイオ燃料向けにトウモロコシなどの食料を利用することに、どのような姿勢を打ち出すかだったが、結局は玉虫色の内容に落ち着いた。アメリカでは生産する3割のトウモロコシがエタノール製造工場に持ち込まれる。バイオ燃料ブームが、急騰した国際穀物相場を押し上げる大きな要因だが、ブッシュ政権は頑なにバイオ燃料政策の転換を拒んだ。食料を使わない次世代のバイオ燃料技術開発の促進を掲げることで、現実に直面している課題から目をそむけた。シカゴの先物市場に大量に流れ込んだ投機マネーについての明確なメッセージにも欠けたし、食料増産の足かせとなる肥料価格の上昇や水不足の課題などに対しても、明確な指針を出したわけではない。
世界の食料安保を考える時、G8や国連など、国を越えた枠組みだけで解決することはできない。お互いの利害が対立し、すばやい対応をとるのがむずかしいことは今回のG8ではっきりと分かった。国民の生活に責任を持つ各国政府の役割が高くなってきたといえるだろう。