
環境保全の視点で“国産”を問い直す試み
近年、食の安全を揺るがす事件の続発は、消費者の食に対する関心を高め、生産方法が明確な国産農産物を再評価する動きを生み出す効果ももたらした。しかし“国産”であることの意味が、農産物の“質”のみから語られる今の風潮は、どこか片手落ちではないだろうか。

―“安全な食べ物”という発想自体が馬鹿げている。そもそも、安全でないものは“食べ物”と呼ばないはずです。それは大前提として、“食べ物”というのは、「常に一定量なければならない」ことのほうが大事なのではないだろうか。石油エネルギー、購入する肥料や農薬、そうした農業資材にできるだけ頼らず、できれば全く頼らないで、何百年、何千年と持続できる。それが本当の農業の姿ではないだろうか。最近、そう思うようになったんですよね―と話す人物がいる。
山形県藤島町の助役を務める相馬一広さん。昨年まで20年近く、月山の山麓で有機農業を営む農業法人 「月山パイロットファーム」代表として、農業を営んできた。それが昨年春、突如、藤島町助役に抜擢されたという珍しい経歴の持ち主だ。
藤島町は山形県酒田市と鶴岡市にはさまれた、人口約1万2000人の町。稲作中心の農業が基幹産業であるこの町は、昨年12月、「人と環境にやさしいまちづくり条例」を制定。有機農業・資源循環・地産地消の推進、農村型生活スタイルの確立、都市住民との交流推進など7項目からなる「エコタウンプロジェクト」をスタートさせた。このプロジェクトの草案を作成したのが相馬さんだ。
「環境保全のひとつの装置としての農林業のあり方という視点が、必要ではないかと思うんです。二酸化炭素の循環も植物なしにはできない。その意味でも、農林業が環境保全に果たす役割は大きいはずです。また、国土に人間が適度にちらばって、農林業をそれぞれ営んで一生を終えることは、この国土を保全する役割にもつながっている。一方、都市に住むひとたちは、そこで生産されたものを消費することによって、結果的に国土保全や環境保全を担う。その循環が“国産”の重要な意味ではないかと思うんです」
環境保全の装置であるはずの農業が、周囲の環境を悪化させては話にならない。農薬や肥料を極力使わない農業スタイルを、地域ぐるみで確立し、人間の生活の営みから生み出された有機物や二酸化炭素を、農業生産のなかに組み込んで循環させる仕組みを作る。農薬や肥料を飛散させず、有機物を“ゴミ”にせず、それによって、土も水もなるべく汚さない。生態系の循環の輪を壊さず、そこから生み出される収穫物を少しだけ人間がもらう。相馬さんは、そんな農村の理想を描いている。
「農業は、単に、“食べ物”を生み出すだけの装置ではない。まして、そこから収益を生み出す道具だけではないはずです」
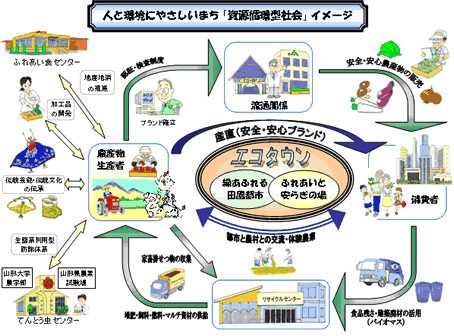
図1 人と環境にやさしいまち「資源循環社会」イメージ
“農の近代化”の功罪を肌で感じた日々
稲作農家の長男として生まれた相馬さんが、山形大学の農学部を卒業後に就農した1970年は、農業の機械化が進み、規模拡大と農薬・肥料の多投入による“農の近代化”路線真っ盛りの時代だ。
「この辺りでは、当時はまだ出稼ぎがさかんだったこともあって、水稲だけでなく他の品目も加えた複合経営の必要性が指摘されていました。私も、父から受け継いだ3.8haの水田のほかに、乳牛のオス仔牛肥育を加えた複合経営を始めて、拡大路線一辺倒で規模を拡大していったんです」
当初12頭だった肥育牛は、40頭程度まで増やした。水田も、地域で売却の話が出ると借金をして買い求めた。農薬や肥料など、新しい資材を存分に使いこなして、規格のそろったものを大量に作る。それが農業経営の理想とされていた。しかし、相馬さんは次第に、自分自身の営農スタイルに疑問を感じ始める。
「牛の頭数を無理して増やすと、牛の事故が起こる。牛が死んでいるときは、朝、牛舎に入ると、すぐ空気でわかるんですよね。しかも、結局、頭数を増やしても利益はあまり変わらなかった。技術が伴わない、やみくもな規模拡大に疑問が出てきたのが、その頃でした」と相馬さんは振り返る。
水田農業でも、当時はホリドールやパラチオンなど、毒性の強い有機水銀剤や有機リン剤さえ、まだ使用禁止になっていなかった。夜を徹して集落ごとに共同防除を行い、毒性の強い農薬を散布した後は、赤旗をたてて水田を囲む。約1週間は立ち入り禁止の合図だ。川で泳ぐのも禁じられた。ホタルや水生生物が、急速に農村から消えていった。
「除草剤も出始めの頃で、PCPなど魚毒性の強い農薬を振ると、田んぼ一面が急にざわざわと動き出して、やがてぴたっと静かになる。田んぼにいたドジョウやオタマジャクシが、ぴたっと死んでしまうんですよ」
もちろん、農作業はラクになった。田植え以後、収穫までの労働の大半を占める草取りが、たった一袋の除草剤で済んでしまう。その恩恵は捨てがたかった。
「その一方で、小さい生き物の展示場みたいだった水田が、なんの生き物もいない、砂漠のような空間に変わっていった。できれば自分の子供には、こうやって作ったものを食べさせたくないという思いと、昔のような重労働に戻るのもいやだ、という思いと。葛藤がありました。当時は有機なんて言葉も社会的に認知されておらず、昔の農法に戻っても、誰が評価してくれるわけでもなかった」
月山の山麓で“有機実験農場”を作る
転機が訪れたのは1977年。東京に出稼ぎに行っていた知り合いの農家、石井甲さんを通じて、「日本有機農業研究会」への入会を勧められたのだ。農業研究者や生協など消費者グループ、農業者によって1971年に設立されたこの研究会は、近代農法に対し、「本来あるべき農法」という意味合いを込めて「有機農業」という造語を掲げていた。相馬さんは、自分と同じ疑問を持つ消費者がいることを改めて知った。
ちょうどその当時、藤島町近くの月山では、山麓を開墾して500haの農地を造成する国営パイロット事業が行われていた。その地を訪れた当時の日本有機農業研究会代表幹事、故・一楽照雄氏に、「農薬も化学肥料も一度も散布されたことのないこの場所に、有機農業の実験農場を作らないか」と話をもちかけられた。栽培された農産物の販路として、都内に本部を置く生活クラブ生協も紹介してくれた。
そこで、まずは石井さんと2戸で月山山麓の畑を4ha借りた。家族の反対を押し切って入植を決めた相馬さんは、当時28歳。結婚して2児の父になっていた。
「水田と畜産があったので、畑が失敗しても生活に困るということではありませんでした。ただ、将来的には絶対に、農薬を使わず、消費者と提携して生産する形で農業をやりたいという気持ちでした」
しかし、なにせ表土を削り取った荒れ地。草の種もないから雑草も生えないかわり、赤茶けた土のなかに、ごろごろと石がころがっている。30分も土を耕していると、ロータリーの爪が半分以上折れてしまう。むき出しの大地だから、せっかく堆肥を入れて耕しても、ひと雨降るだけで何メートルも表土が流される。およそ畑とは言い難かった。植え付け作業をしながら、「これは芽が出ないかもしれない」と相馬さんは思ったという。
馬鈴薯の植え付け作業後、“本業”の水田に戻って代かき、田植え作業を終えてから、半月ほどして再び月山を訪れた。濃霧のかかる山道を車で上り、農場に着くと、白い霧の合間にまっすぐと、緑色の筋が見えた。
「なにか、胸にぐっと来たのを覚えています。こんな荒れ地でも、芽を出す作物の力に感動したんですよね」
もっとも、1年目の馬鈴薯の出来は散々だった。20トンの契約数量に対して、収穫はわずか10トン程度。しかも半分は、そうか病が発生したり、ピンポン玉のように小さい規格外品だった。それでも、その馬鈴薯を全量引き取り、翌年も提携を続ける姿勢を見せた生活クラブ生協に、産直提携のありがたさと、生産者としての責任を実感させられた。
「作るだけでは、農業は成り立たない。食べてくれるひとがいて、初めて成り立つ。循環という視点で見れば、消費者も生産者も立場は同じで、生産者・消費者という分け方自体がおかしいんです」
作物が自然に育つ永続型農業をめざす
やせた土地を改良するため、さまざまな市販の土壌改良材も使ってみた。しかし、「経営面積が狭い施設栽培なら成り立っても、土地利用型農業で、10aの粗収益が10万円あればいい月山の畑では意味がなかった」
やみくもに堆肥を入れても、土は変わらない。それなら、この土地に合う作物があるはずだ。栽培品目を選び、輪作によって農薬ゼロをめざし、化学肥料も減らしていく方針を立て、以後10年間、白菜や山ごぼう、ニンジンなど約40品目の試験栽培をしながら輪作体系を模索した。
15年ほどかけて、ようやく完成した輪作体系は、ナス科のジャガイモと、アブラナ科(赤カブ・青菜)、ユリ科(ネギ・あさつき)、セリ科(にんじん)、マメ科(だだちゃ豆・青大豆)、イネ科の6種類を5年に1回という基本パターンだ。これに堆肥を10a当たり3トン投入する。これで、殺虫剤や殺菌剤、土壌消毒ほぼゼロの基本パターンができた。
現在は、さらに堆肥の投入量も減らす「低投入持続型農業」をめざして、新たな輪作体系の実験を行っている最中だ。
たとえば、窒素固定機能のあるマメ科の作付けをさらに増やして、窒素肥料を減らす。土壌中のリン酸の吸収率を上げるひまわりを輪作体系に入れる。
「農業は、収穫物の形で必ずものを収奪する。なんらかの形で収奪した分を土に戻さなければいけません。問題はその戻し方。輪作体系を工夫することで、堆肥も半分から3割程度まで落としても持続できる農業ができないか。ゆくゆくは、いろんな作物の種をまくだけで、永続的に農業生産ができる、尽きることのない食料庫のような農場にならないかという思いがあるんです」
近代農業では、ハウスで人工的な空間を作り、いかに作物に季節を錯覚させて抑制・促成栽培するか、いかに収量を上げるかが高度な農業技術とされてきた。相馬さんは、この流れに一線を画す。キーワードは“持続できること”だ。
ちなみに、栽培してみると、地域で昔から伝承されてきた、いわゆる“伝統作物”が、資材をあまり入れなくても育つ強さを持っているという。
「赤カブなどは、ぱらぱらと種をまいて、ほうきでならすだけで勝手に生えてくる。だだちゃ豆やアサツキも、実に生命力が強い。結局、気候・風土に合ったものがその土地に伝承している。それが、その土地の食べ物としても自然なものだと思うんです」
食のグローバル化と石油文明は永続しない
作物が勝手に育つ農場をめざすのは、「大量の堆肥を山の上までトラックで運ぶことで、石油エネルギーを大量に使いたくない」という思いがあるからだ。
「植物の力だけで、あとはちょっと手を加えるだけで自然に育つようになれば、かりにトラックが動かなくなっても、畑のなかで循環できるじゃないですか」
相馬さんが話す「食料自給」や「国産」の意味も、この延長線上にある。
「輸入農産物を買いあさる今の日本の食生活が、いつまでも続くとは思えない。広域流通を可能にしているのは、石油エネルギーです。どんなに楽観的に見ても、それが永続するとは思えない。カネさえ出せば、いつでもどこからでも食べ物が来る状況が1000年も続くはずがないんです」
現在、輸入農産物を生産面積に換算すると約2000万ha。そこから農産物の形でリン酸や窒素が大量に日本に持ち込まれ、循環しないまま国内にたまり続けている。このままでは、次の世代に大きな負の遺産を残すと相馬さんは危惧する。
結局は、自分たちの周囲の海なり山なり森なりの土地を使いながら、そのなかで質素に命をつないでいくのが持続的ではないか。多少は広域で食品のやりとりがあってもいいだろうが、基本は、自分たちの住む環境のなかで作られるものを食べて生きることだと相馬さんは考えている。
「地球という限られた環境のなかで、人間も自然循環の輪のなかの1個の有機体でしかない。そのことを理解すれば、消費も生産も、もっと慎ましやかに変わらざるをえないと思うんですよね」
(農業ジャーナリスト 榊田みどり)
